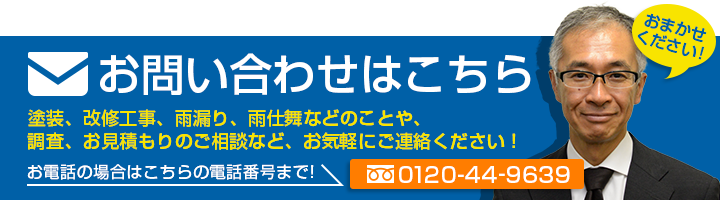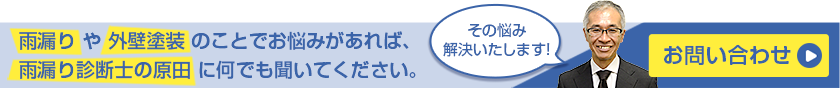【大屋根リングについて】X(ツイッター)を更新しました

【速報】万博・大屋根リングの一部で『雨漏り』博覧会協会「原因を調査し施工業者に対応依頼していく」ゲート前で通信しづらい状況は「入場へのスムーズな運用改善に努める」
4/14(月) 9:47配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/ac4385198737a77f827d50a569bc421bfb7e5a79
こちらの記事について
我々雨漏りに携わる実務者は、、、と申しますと、私と異なる見解をお持ちの方に迷惑をかけてしまうことになりかねないので、あくまで私のこととしてお伝えします。
私は超能力者ではないので、一見して雨漏りする建物であるか否かを断定する能力はありません。ただし、雨漏りするリスクが高いか否かは、感覚としてわかります。このことをして私の能力が高いと申し上げるつもりは毛頭ありません。反対に、着眼点さえ明確になれば、誰しもが理解できることなのです。
大屋根リングに関しては、軒が明確ではありません。一応柱よりも外側に軒が張り出しているようです。でも、軒先と横架材の先端がほぼ同一の垂直面上にあるため、横架材には通常の降雨でも雨がかかるものと推測されます。

軒の出は、傘をイメージするとわかりやすいです。折り畳み傘のような小さな傘では、肩や腕に雨がかかってしまいますが、大きな傘になればなるほど濡れる程度は少なくなります。したがって、軒を長く出せば、暴風雨にもならない限り垂直面に雨がかかりません。だから、特に木造の建築物においては、軒は極めて重要な設計上の工夫です。

また、同じく有機系防水材がなかった時代にはありえなかったデザインを採用しています。それは「陸屋根」です。平らな屋根は水が溜まってしまうため、かつては、腐朽する木材に対してはタブーな設計でした。建物と同様の建材を用いて造作されたバルコニーが一般的になったのは「自在に形を変えることができ、密着性があり、なおかつ水を通さない」有機系防水材が流通しだした1980年代以降です。そのバルコニーにしても、建物の一部であることが圧倒的で、多くは勾配屋根によって雨水の浸入を防いでいます。
そんな陸屋根ですが、全長2キロのほぼすべてが「スカイウォーク」と呼ばれる床になっている建築物は、雨漏りのリスクに関しては、残念ながら低くはないといえます。

そして、極め付きは「屋上緑化」です。スカイウォーク部分を含め、約32,500平方メートルの面積が緑化されているそうです。植物は根から吸水していますので、土が必要です。しかも、その土には多くの水を含んでいることが求められます。言い換えれば、屋根の表面が常にびしょびしょに濡れている環境が必要なのです。これは、雨水浸入を防止する仕組みとは対極にあるといえます。
ここまでお伝えした内容、すなわち「軒の出」「勾配屋根」「水を溜めないこと」などは、雨水浸入を防止するための、ある共通する考え方がベースになっていますが、お気づきになられましたでしょうか。
それは、「建築物に影響を与える雨水を管理するための仕組みや工夫」です。実は、単なる「防水」では、その仕組みや工夫は考慮されません。防水と言う概念には、防いだ水をどのように排出するかまでは含まれないのです。だから、いくら防水しても雨漏りする建物や、逆に防水したらかえって雨漏りするようになった建物が多く存在するのです。
では、「建築物に影響を与える雨水を管理するための仕組みや工夫」ですが、これが、私が考えるところの「雨仕舞」の定義です。雨仕舞は防水ではありません。そもそも雨がかからないようにする、雨がかかる場合には速やかに排出させる、雨がかりする箇所は乾きやすくする、などを現実化させるための「仕組み」や「工夫」です。
雨仕舞の考えがないと、いくら防水してもそのうち雨漏りします。なぜなら、材料は劣化するからです。対して、雨仕舞の基本である「仕組み」や「工夫」は劣化しません。
最後に、この記事に関し、大屋根リング、ひいては万博を否定する意図はありません。私がライフワークとしている、建物の耐久性における検証のサンプルとして例示したまでですので、その旨ご理解いただけますと幸甚です。
また、私の知見の及ばない新機軸がなされているかもしれませんので、詳しい方がいらっしゃれば、ぜひともご教示いただきたく存じます。
※先ほど、今回の漏水は雨漏りではなく雨どいからの越水であることが原因とみられるという報道が出ました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/1d19464f6ce0548b41ed10a1978aacfb83e17f7e
本記事は、雨漏りのリスクについての記述ですので、そのまま掲載する判断をいたしました。